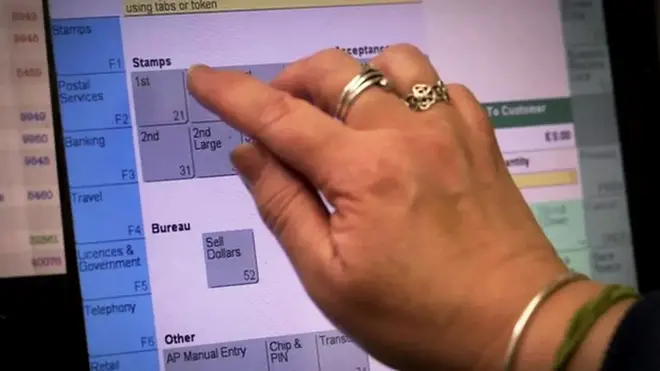【解説】 富士通と英郵便局スキャンダル どう関係しているのか
大井真理子、BBCニュース(東京)

「イギリス史上最大の冤罪(えんざい)事件」と呼ばれる郵便局スキャンダルで、会計システムを提供していた富士通が下院で証言するにあたり、その対応に再度注目が集まっている。しかし、900人以上の郵便局長らが横領や不正経理の無実の罪を着せられたこの事件を知る人は、富士通の本社がある日本では少ない。
富士通は、イギリスで郵政の窓口業務を担当する会社「ポスト・オフィス」にソフトウェア「ホライゾン」を納入した。その欠陥が大規模な冤罪につながったが、同社では誰も責任を問われておらず、被害者への補償金も一切支払っていない。
その一方で、富士通は英政府のITサービス関連の高額契約を獲得し続けている。
「ホライゾン? ホライゾンって?」
これは、「ホライゾン」の欠陥について、富士通の元社長に質問した時の反応だ。郵便局長らは、窓口の現金とこのシステム上の記録額に不整合が生じていたことから犯罪者とされた。
40年近く富士通に勤務し、英コンピューター企業ICLを買収した時のことは覚えている彼も、システム欠陥については知らなかったと言う。
英政府が横領罪で収監された郵便局長たちの上訴を迅速化しようとする中、富士通本社は堅く口を閉ざしている。
2022年に取材依頼を広報IR室に断られた後、時田隆仁現社長に直接、話を聞かせてもらいたいと幾度もメールをした。「理不尽な有罪判決を受けた方たちに対して、例え一言だけでもコメントがないか」と。
しかし答えは、「本件英国現地法人が一元的に対応しておりますため当社からの具体的なご回答は控えさせて頂きたく存じます」というものだった。
そして今週、再び取材依頼を断られた際のコメントは以下のようなものだった。
「富士通はこの問題を厳粛に受け止めています。法定調査では長年に及ぶ複雑で機微な出来事の調査が進められており、英国子会社が全面的に協力しております。調査への影響を考慮して、これ以上のコメントは差し控えさせて頂きます」と述べた。
裁判になるまで、本当に本社のトップが知らなかったのだろうか? 疑問に思う人も多いだろう。
しかし現地法人の社員と話すと、そうだとしてもあまり驚きはない。
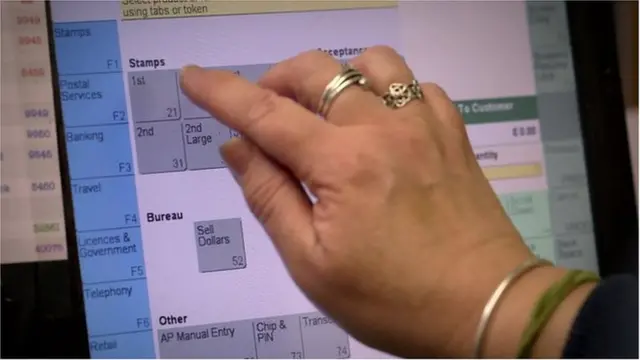
「日本には言うな」
「富士通UKは、名前が変わっただけで、今でもICLのままだ」と言うのは、匿名ならと取材に応じてくれた元社員。
彼女いわく、2004年から2008年まで富士通UKの社長だったデイヴィッド・コートリー氏の口癖は「Keep Japan out(日本には言うな)」だった。入社当初、同僚の多くが日本に一度も行ったことがないことを知って、彼女は驚いたという。
ICLと富士通の関係は何十年も前にさかのぼり、両社のオペレーションには似ている部分も多い。
1970年代、日本とイギリス両国は米IBMに対抗しようとしていた。英政府はICLを設立した。
日本では通産省(当時)による行政指導の下、1972年3月に国内6社が3つの企業連合(富士通・日立、日本電気・東芝、三菱電機・沖電気)を構成し、技術研究組合を創立した。
国際競争力を付けるための補助金制度が整えられ、企業連合は1976年までに約570億円の補助金を受けた。
政府のバックアップを受け、日本企業は海外で買収を繰り返した。当時の為替レートも手助けとなった。
ちょうどその頃、イギリスではICLが金銭問題を抱え出した。1981年に赤字を出した際、当時のマーガレット・サッチャー首相は支援を拒んだと言われている。
よって、富士通とICLは完璧な組み合わせだった。
ICLを買収した富士通は、イギリスで並外れた存在感と英政府との緊密な関係を得た。一社応札のかたちで政府から受注することも多かった。
「富士通ICLは英サプライヤーとしてイギリス政府に優遇されていた」と、ソフトウェアコンサルタントのジェイムズ・クリスティ氏は話す。
「私がIBMに勤めていた時、我々はスコットランドでコンピューターを作っているのにアメリカ企業として扱われ、日本でコンピューターを作っているICLがイギリス企業として扱われるのは皮肉だと同僚と笑っていた」と言う。
「富士通なしにはまわらない」
郵便局スキャンダル後も、富士通UKは英政府から受注を続けている。
政府の契約などを分析している英タッセルによると、富士通は過去4年間で101件の契約を獲得し、総額は20億ポンドに上る。ホライズンの延長契約には9500万ポンドが支払われた。
ただ、富士通側が開発したシステムには、ホライゾン以前から問題が生じていた。
たとえば1999年に富士通ICLは、英治安判事裁判所の事案管理ソフトウェア「リブラ」の開発契約を1億8400万ポンドで受注したが、予想の約3倍のコストがかかった上、最終的に会計検査院はリブラについて、基本的な財務情報も提示できないと結論付けた。
ホライゾンは同時期にポスト・オフィスに導入されたが、その問題点はすでに知られていた。なぜなら、ホライゾンは元々は1994年に発表された給付金支払いの自動システムに使われるはずだったが、その基準をクリアできていなかったからだ。
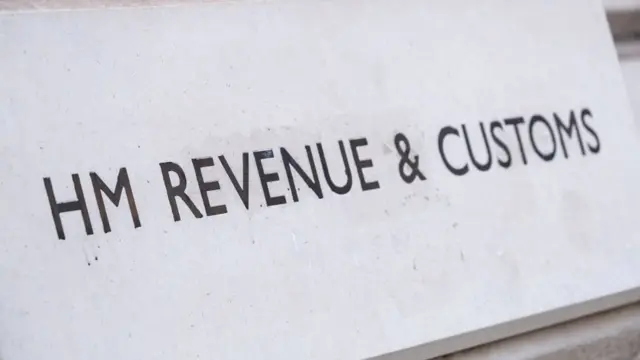
画像提供, Getty Images
長年IT業界を取材しているトニー・コリンズ氏は、「ポスト・オフィスはホライゾンという失敗作を押し付けられた」と話した。
2004年には、富士通UKは国民保健サービス(NHS)のデジタル化を他3社と任される。しかし度重なる遅れのためNHSが契約を断ち切ると、富士通は訴訟を提起。NHSが敗訴し、イギリス政府は7億ポンドの支払いを命じられた。
その時の経験から、ポスト・オフィスのことで富士通を訴えることを避けているのではないか、と言う専門家もいる。
しかしこれほどの問題を抱えているにもかかわらず、英政府は富士通を断ち切るつもりはないとコリンズ氏は言う。
「もし富士通がポスト・オフィスのプラグを抜けば、そういうことはしないだろうが、郵便局は機能しなくなる。政府は富士通なしでやっていけない」
コリンズ氏によると、富士通は税務当局、歳入税関庁(HMRC)、労働・年金省などの政府機関に大規模なITシステムを提供しているという。
日本国内でも問題に
富士通のソフトウェアは、日本国内でも話題になっている。
昨年は、マイナンバーカードを使ってコンビニで証明書を交付するサービスで、別の人の証明書が発行される不具合が相次いだ。
また2020年には、東京証券取引所と富士通が共同開発したシステムの障害で、株式全銘柄の売買が終日停止となった。
2005年にも東証が誤発注を取り消せず、400億円を超える損失が出たが、当時の基幹システムを開発したのは富士通だった。
また、2002年のみずほ銀行のシステム障害では、富士通など3社が批判を浴びた。
NTTとマイクロソフトで勤務していたソフトウェア・エンジニアの中島聡氏は、「エンジニアを正社員として雇いたがらないビジネスモデル」に原因があると言う。
終身雇用制が根強い日本では、アメリカのように社内でエンジニアを雇用すると固定費が増えてしまうため、企業は社外のシステムインテグレーションベンダー(SIer)に外注してきた。
その結果、多重の下請け構造が生まれ、クオリティーにも影響がでていると言う。

画像提供, Getty Images
池上純平氏は東京大学を卒業後、2015年に富士通にシステムエンジニア(SE)として入社した。
「最先端の技術を使っているというよりは、昔の技術を使って大きいシステムを保守している現場を目の当たりにしました。最先端の生産性の高いシステム開発を経験できない気がして、成長できる環境を探して転職活動をしました」と、池上氏は話す。
それでも富士通は、日本ではなお大きなIT企業だ。
「富士通の強みは政府との強いつながりだ」と中島氏は言う。
「政府との関係がなければ、競争性はない。自由で開かれた市場では、富士通のような会社は何十年も前に消えていたと私は思う」
富士通の対応に注目が集まるイギリスでは、現地法人がかつてのような政府の優遇を受け続けることは難しそうだ。