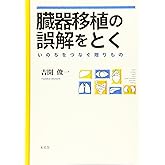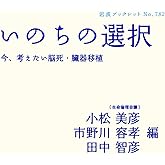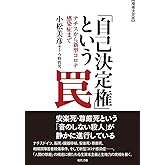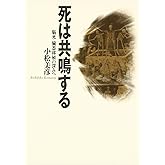本の内容が物凄い。脳死について踏み込んで理論や問題点を展開しており、読み応え&啓発される。

無料のKindleアプリをダウンロードして、スマートフォン、タブレット、またはコンピューターで今すぐKindle本を読むことができます。Kindleデバイスは必要ありません。
ウェブ版Kindleなら、お使いのブラウザですぐにお読みいただけます。
携帯電話のカメラを使用する - 以下のコードをスキャンし、Kindleアプリをダウンロードしてください。

脳死・臓器移植の本当の話 (PHP新書) 新書 – アドベントカレンダー, 2004/5/17
小松 美彦
(著)
このページの読み込み中に問題が発生しました。もう一度試してください。
脳死者の臓器提供をめぐる問題に何があるのか? 「臓器移植法」改定を前に、長年の論争の焦点を整理する。生命倫理の本質をえぐった渾身の大作。
「脳死者は臓器摘出時に激痛を感じている可能性がある」「家族の呼びかけに反応することがある」「妊婦であれば出産できる」「19年間生き続けている者もいる」――1997年に「臓器移植法」が成立して以来、日本でも脳死・臓器移植は既成事実となった感が強い。ところが近年、脳死を人の死とする医学的な根本が大きく揺らいでいるのだ! 本書は脳死・臓器移植の問題点を、歴史的、科学的に徹底検証。報道されない真実を白日の下にさらし、「死」とは何か、「人間の尊厳」とは何かをあらためて問い直す。68年に行なわれた和田移植、99年の高知赤十字病院移植の綿密な比較検討から浮かび上がる衝撃の新事実に、読者の目は大きく見開かれることだろう。
読者の道案内役をつとめてくれるのはサン=テグジュペリ作「星の王子さま」。「心で見なくちゃ、ものごとはよく見えないってことさ」という言葉が問題を解くカギとなる。
- ISBN-104569626157
- ISBN-13978-4569626154
- 出版社PHP研究所
- 発売日2004/5/17
- 言語日本語
- 本の長さ424ページ
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
ページ: 1 / 1 最初に戻るページ: 1 / 1
登録情報
- 出版社 : PHP研究所 (2004/5/17)
- 発売日 : 2004/5/17
- 言語 : 日本語
- 新書 : 424ページ
- ISBN-10 : 4569626157
- ISBN-13 : 978-4569626154
- Amazon 売れ筋ランキング: - 71,693位本 (本の売れ筋ランキングを見る)
- - 148位PHP新書
- - 1,108位生物・バイオテクノロジー (本)
- - 19,342位ノンフィクション (本)
- カスタマーレビュー:
著者について
著者をフォローして、新作のアップデートや改善されたおすすめを入手してください。

著者の本をもっと見つけたり、似たような著者を調べたり、おすすめの本を読んだりできます。
カスタマーレビュー
星5つ中4.2つ
5つのうち4.2つ
42グローバルレーティング
評価はどのように計算されますか?
全体的な星の評価と星ごとの割合の内訳を計算するために、単純な平均は使用されません。その代わり、レビューの日時がどれだけ新しいかや、レビューアーがAmazonで商品を購入したかどうかなどが考慮されます。また、レビューを分析して信頼性が検証されます。
上位レビュー、対象国: 日本
レビューのフィルタリング中にエラーが発生しました。ページを再読み込みしてください。
- 2013年6月18日に日本でレビュー済みAmazonで購入幾つかの先行レビューにあるとおり、大変勉強になる本だと思います。
(1) 私は元々、臓器移植は現代医療技術が生んだ、現代版フランケンシュタイン博士の「怪物」の一つだと思うし、1882年以来の「心霊研究」の成果が、「魂は永遠」であり、我々は何度も「生まれ変わっている」ことを示していることを正しく理解すれば、そもそも臓器移植の考えは「唯物論科学」が生み出したばかげたアイデアの一つなのだなと結論します。従って、このテーマにはたいした興味を持っていませんでした。
(2) 私がこの本を読んだきっかけは米国製のシリーズもののあるテレビ・ビデオ(The Firm)を観たことによる。この番組のあるエピソードで、男性の死刑囚が次のような提案をする:自分はさんざん人殺しを重ね、死刑になって当然なのだが、最後に何か一つ「良いこと」をして死にたい。自分が殺したある男性の娘(14〜15歳か)は重い心臓病で、心臓移植の順番待ちにあるようだ。自分の心臓を提供したい。
(この死刑囚の母親の夫が関わる事件を担当していた、映画の主人公の弁護士が当該母親から、息子の思いを何とか実現できないか、と依頼される。ところが、この死刑囚の死刑執行は数日中なのだが、死刑は3種の薬を用いた薬殺によるもので、その薬の中には死亡後の心臓が移植には使えなくしてしまうものがあり、当該弁護士これを何とかしなければならない羽目に陥る。)
(3) 私はこのビデオで、死刑囚が「自分の心臓を提供したい」と言い出したとき、えぇつ、本気なの!と思った。その理由は、死刑囚の思いに感心したのではなく、そんなことをしてまで、自分が娘の身体の中でさらに生き延びる積もりなのか、と早合点したからである。私はこの時点で、臓器移植の提供者と受給者が関わる「衝撃的な事実」を、米国のある大学の科学哲学者が書いた本から知っていた。(Immortal Remains: the evidence for life after death, by Stephen Braude, 2003)
(4) この本の第7章(The Lingering Spirits(永く続く魂))の7.4、7.5節に、臓器移植の先進国である米国で、臓器の提供を受けた患者が移植後の人生で、自分が「変わってしまった」ことに気がついたことが書かれている。著者Braudeによると、このような現象が一般の人々に知られるようになったのは、ある男性の心臓と肺の同時移植を1988年に受けた女性Claire Sylviaが、1997年に本「A Change of Heart (心の変化、とでも訳すか)」を書いたことに端を発したと言われる。移植後、彼女の性格、嗜好などががらりと変わり、ドナー側の家族からの情報によると、新しく彼女に顕れた性格、嗜好は、ドナーのそれであることが分かった。
(5) Braudeの本には、他の研究者による調査結果で、関連する医学雑誌に発表された(1999年)ものが4ケースほど引用されている。いずれのケースも「衝撃的」である。その一つ(Case 3)の概略を紹介しよう:生後16ヶ月、風呂でおぼれて死亡した男児(名前Jerry)の心臓の提供を受けた、生後7ヶ月の男児(名前Carter)のケースである。ドナーJerryの母親は内科医であり、彼女は次のように語っている:「レシピエントのCarterが幼いとき、私に最初に合ったとき、彼は私に走り寄って、抱きつき、その鼻を私のそれに押しつけ、私の鼻をさするのでした。その行為は、まさに亡くなった息子のJerryが生前に私に対してしたことなのです。」「私はドクターです。私は、鋭敏な観察者であるように訓練されてきたし、生まれながらの懐疑論者です。しかし、これは事実なのです。・・・」
心臓移植を受けたCarterは、幼い頃、両親と教会のミサに少し遅れて行った折、母親の手を振り切って、合ったことのないJerryの父親に駆け寄って、そのひざに乗り「お父さん」と叫んだのだそうです。母親は、本来内気なCarterがそんなことをするのに戸惑うのです。このケースを調査した研究者が、Carterに、なぜそんなことをするのか?とたずねる、Carterは、それはJerryがしているのです、と応える。
(6) 臓器移植が成功裏にゆく確率を上げるには、医者等がつくり出した「脳死」と言う概念で法律上の「死」定義し、その「死」と判定された時点で速やかにドナーから臓器を取り出し、これを速やかにレシピエントに移植することが必要となることは、小松美彦氏によるこの本が詳述している通りである。日本で採用されている「脳死」概念は、著者が書いているように、基本的には、臓器移植先進国の米国で生まれた概念である。そして、上述したClaireとCarterのケースでも同様の基準に従って臓器移植が実施された。その結果、上で引用したような、唯物論科学の観点からは考えられない、「驚くべき事実」が起こっているのである。つまり、「脳死」の状態ではドナーの「意識・記憶」が臓器に残っている、と考えざるをえない。これが果たしてドナーの「死」と言えるのだろうか?? それが小松氏の問うところであろう。
(7) このように書くと、それでは「心臓停止」後に取り出した臓器では、仮に移植が成功したとして、ClaireやCarterのケースのようなことは起こらないのか??という疑問が出るであろう。私にもその答えは分からない。実際にデータを集めなければ分からないだろう。
私がこのようなことを書く一つの理由は、人の「魂」は恐らく「死」を超えて存続するのだろうと考えるからである。その根拠の一つは、1907年に発表された、「魂の重さ」を測った実験の論文にある。世の主流科学者等はこの論文を「無視」しているが、私は最近この実験をニュートン力学に基づく理論計算により模擬してみた。その結果を、下記の科学誌に論文として発表した:
「Journal of Scientific Exploration, Vol. 24, No.1, pp. 5 - 39, 2010: Rebuttal to claimed refutations of Duncan MacDougall’s experiment on human weight change at the moment of death」(amazon.co.jp またはamazon.comから購入可能)。
この論文の結論は、
[1] マクドゥーガルの実験には、批判されているような「欠陥」は無い。
[2] 彼の実験結果は、一重に「他の科学者による確認実験」を待つのみであり、既に110年以上経た今日も、それがなされていないと言う嘆かわしい状態にある。
というものである。
何年か前に「21グラム」というビデオが米国でつくられ、今もレンタル・ビデオ店で借りられる。このビデオの「タイトル」はこの実験に由来する(ただし、ビデオの中にこの実験の話は出てこない。「魂には重さがあるのだろう」という考えが一般の米国人には社会通念としてあるということである)。
(8) 私は、米国人の多くがこのような事実を知っているものと仮定したために、上記のビデオのエピソードを見た折にびっくりしたわけです。このビデオの物語の原作者は、よく知られたジョン・グリシャムで、彼も上記の「事実」を当然知っているでしょう。ビデオの話をおもしろくするために、その様な事実は度外視したのでしょう。
(9) 「臓器移植」後進国の日本とはいえ、上記のような「事実」を、日本での経験を待ってから議論する必要はないはずです。私は財布の中に持参している健康保険証の裏面にある「臓器提供」に関する意思表示の欄には、「しない」と表示しているが、その理由の一つは上記のような「事実」があることによるもので、臓器移植によって他人の身体に私の「意識」の一部を存続することはしたくないとの理由によるものです。
(10) 臓器移植ではレシピエント側に感動的な話が多いが、これらは現代医療技術がもたらした産物なのだろう。同じ技術は、最近ではips細胞による再生医療の実現の話を生みつつある。私は、ips細胞の話がノーベル賞受賞で7時のNHKTVの話題になったとき、夕飯を食べながら、これは現代版の「フランケンシュタイン」物語だな、とWifeにつぶやきました。
- 2021年10月8日に日本でレビュー済みもう十年以上前ですが、脳死状態の祖母の臨終に駆けつけた際、瞳孔は完全に開き、自発呼吸もできず(肺が水浸しの状態と言われた)、管だらけで全身がぱんぱんに浮腫み、「意識は既に無い脳死状態」と告げられました。
親族が揃うまではそのような状態で延命措置が続けられていました。
ですが部屋に私と二人きりの時、微かに顔を私の方に向けて呂律の回らない、言葉にならない声でゆっくりと「あいがおう…」のようなことを言いました。
私にはそれは「ありがとう」としか聞こえなかったのですが、その言葉のあとで、瞳孔がぽっかり開いた両目から涙を流したのです。
親族はなかなか信じようとしませんでしたが。
水を飲ませることを禁じられていたこともあり、口の中を覗くと祖母の咽頭は幾筋も深く裂けてしまっており(痰の吸引がまだ行われていたことも影響していたのかも)、まるでタコさんウインナーの太い足のように喉の粘膜が何本もめくれているような有り様でした。
どんなにか痛いだろうと。。
末期の水も飲ませてやれないのがあまりに辛く、看護師さんに懇願したところ、「スポンジの先にほんの少しだけなら」ということで、祖母の口許に水を浸した小さなスポンジをそっと当てると、むさぼるように必死に吸って水分を飲むのです。
どう見てもこれは意識があると周りで私たち親族は話すのですが、看護師さんは「生体反応のようなものです。もしも魂があるなら今頃は身体を離れて上の方から見ているはずで、ご本人はもう苦しくもなんとも無いんですよ」と繰り返すばかり。
それでも痰の吸引が行われる際は「身体の反応で大変暴れるので、席を外して頂いた方が良い」と告げられ、廊下で待つ私たちはその度に部屋の中から祖母が凄い唸り声を上げて暴れているのがわかり、恐ろしいやら居たたまれないやらで、脳死というものがこれほど過酷な死に方なのかと混乱していました。
そんな祖母は角膜の臓器提供を希望していたため、最終的な脳死判定がなされてすぐ運ばれて行きましたが、痰の吸引でさえあれほど苦しんで暴れていた祖母が、眼球を摘出とは。。阿鼻叫喚ではなかったのだろうか、それで本人は本当に満たされたのだろうか、と心が痛んでやみません。
それまでは私自身も臓器提供を希望していましたが、祖母の死以後は完全に転じて、一切の提供希望をやめました。
想像すらしたくないですが、やはり意識は残っている、としか思えないのです。
- 2006年1月31日に日本でレビュー済みAmazonで購入脳死移植について中立的な立場をとるとする本書ではあるが、基本的には脳死移植のドナーの周辺の状況に少し傾いているきらいはあり、全く中立的とはいえない。しかしながら、脳死の話の際には移植される患者の側が公にされることが多い状況を、ある意味補完しているのかもしれない。元は死の概念は心臓死であった。移植技術の行使のためというか、それほど直接的ではないにしろその技術の到来と同時期に脳死という概念化が行われた。すなわち「頭脳をもって生きられない人間から臓器をもらったり心臓死を及ぼしてもよい定義付け」である。脳死といって死のレッテルをはることで殺害による罪概念を昇華しようとする試み。それは一歩間違えれば危険な匂いがするのであるが、一方で成り立ちがどうであれ、現実のなかで変容を遂げ出発点とはまるっきり違って現実にすっぽりとはまってしまう事柄もある。出発はどうであれ人々が脳死という概念と仲良くやっていくのであればそれはそれで良いとも思ったりする。こんな文章を書いている途中に病院内で人工心臓を携えて歩く患者をみて、やはり何とかしてこの人工心臓をとれるような状況を作り出したいとも切に思う。その思いもきわめて切実である。この本で書かれているように「統計的には移植しなくても生存曲線は変わらず、移植の意味自体問う必要がある」という論調は現実を前にしては空しい感がある。
- 2013年6月15日に日本でレビュー済みAmazonで購入何となく感じていた脳死臓器移植問題に関して、論理的かつ厳密に論じている。
心臓が拍動している脳死者から臓器を摘出すること(=これにより完全に死ぬ)は、
臓器移植法施行以前は殺人で、以降は合法的行為となる、というのは確かに
奇妙だ。死の瞬間を法律ひとつで後ろにシフトできる、というのは誰でも
違和感を感じるのではないだろうか。
また、本書の最後の方で、脳死者からの臓器摘出の目的のひとつが、
製薬会社による新薬開発のための材料の安価な供給である、とする著者の
おそましい主張には、一瞬度肝を抜かれたが、よく考えると十分にありそうな
話である。健康保険やその他の医療保険も、考えようによっては全て
巨大製薬会社を(必要以上に)潤すために存在しているようなものである。
- 2013年8月12日に日本でレビュー済みAmazonで購入多くの人がそう思うように、私は自分として、人間としての意識がなくなり、考えることもできず死ぬことを待つだけであったら、その体を資源として病気に苦しむ人のために役立てたい、と考えていました。もちろん今でもそういう気持ちはありますが、この本を読むと、それはそう簡単なことではないことがよくわかります。医師たちが自分の家族に「この方はもう脳死です。助かりません。肉体がダメになる前に、不治の病で苦しむ方々に移植して役立てるため、臓器を今から取り出しますね」なんて言う言葉が耳元で聞こえ、体を切り刻まれるときに想像もつかない痛みを感じてもがき苦しむ・・・そういうことがあり得るのです。私は医療関係者ですが、こんなことは知らされていませんでした。これまで手放しで脳死下の臓器移植に賛成していてごめんなさい。知らなかったとはいえ、申し訳ない気持ちです・・・・
- 2020年12月16日に日本でレビュー済みAmazonで購入脳死の患者から臓器を摘出する手術をするとき、麻酔をすることがあることは初めて知りました。やはり、患者は普通は激痛を感じるのだと思います。本書によりますと、NHKのドキュメンタリーでは、臓器を摘出する手術の最中、ドナーは額に汗して、涙を流していたそうです。人は死にますと、通夜で24時間は安置されます。昔からのしきたりでしょうが、理由は知られていません。臓器移植の場合は、脳死ですので、心臓が動いていても摘出手術は行われます。やはり、そこに何か無理があるように思えてなりません。私は、健康保険証の裏に臓器移植に同意しない旨を明記してあります。
- 2005年12月29日に日本でレビュー済みAmazonで購入人の死は、確認する(呼吸停止・心臓停止・瞳孔拡散)死から、判断する死(それも臓器移植を推進する医者が判断する死)へと変わりつつある今日、自分が脳死だと判断される時、本書は密室では何が行われるのかを垣間見させてくれる。
ある英国人医師の言葉が引用されている。「(脳死患者に)メスを入れた途端、脈拍と血圧が急上昇するんですから。そしてそのまま何もしなければ、患者は動き出し、のたうち回りはじめます。摘出手術どころじゃないんです。ですから、移植医は私たち麻酔医に決まってこう言います。ドナー患者に麻酔をかけてくれ、と。」
マスコミは移植を受けて、生命の危機を救われた患者のみを取り上げた番組を美談として執拗に報道し続ける。しかし、一方で提供する側は、密室でこのような光景が展開していると知ると、ドナーカードの所持をもう一度立ち止まって考えさせられる。
著者は「ナチスの蛮行に戦慄する私たちは今、生きている脳死者を死人と決めつけ、あらゆる形で資源化し、商品にして市場に乗せようとしている。その突破口が『臓器移植法』の改定なのだ。」と喝破している。そこまで言い切ることができるかどうかは別として、『臓器移植法』の改定検討が無批判に進められる中で、こうした警鐘が鳴らされていることを知っておくことは大きな意味があると思う。