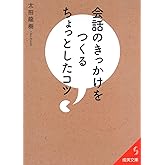Amazonプライム無料体験について
プライム無料体験をお試しいただけます
プライム無料体験で、この注文から無料配送特典をご利用いただけます。
| 非会員 | プライム会員 | |
|---|---|---|
| 通常配送 | ¥460 - ¥500* | 無料 |
| お急ぎ便 | ¥510 - ¥550 | |
| お届け日時指定便 | ¥510 - ¥650 |
*Amazon.co.jp発送商品の注文額 ¥3,500以上は非会員も無料
無料体験はいつでもキャンセルできます。30日のプライム無料体験をぜひお試しください。

無料のKindleアプリをダウンロードして、スマートフォン、タブレット、またはコンピューターで今すぐKindle本を読むことができます。Kindleデバイスは必要ありません。
ウェブ版Kindleなら、お使いのブラウザですぐにお読みいただけます。
携帯電話のカメラを使用する - 以下のコードをスキャンし、Kindleアプリをダウンロードしてください。

ディベートの達人が教える説得する技術 ~なぜか主張が通る人の技術と習慣~ 単行本 – 2006/5/20
購入オプションとあわせ買い
「あの人が話すと、つい頷いてしまうな」
あなたの周りにそういう人はいませんか?
周りからそんなふうに思われれば、仕事でプライベートで
ものごとがスムーズに進むことは間違いないでしょう。
でも、実際には・・・
「どう見ても、自分の意見のほうが理にかなっているのに」
「なんだか言いくるめられてスッキリしないな」
「あまり専門知識のない人に、頭ごなしに反対されて悔しい」
「立場の力で意見を押し切られるなんて理不尽だ」
一生懸命に仕事をするあなたなら、
会議後に、そんな後味の悪い思いしたことはあるでしょう。
それは、あなたの考えや仕事の仕方が間違っているのではなく、
ちょっとした伝え方のコツを見落としていたり、
説得のカラクリを知らないだけなのです!
そこで、周りを説得し動かすための
「説得の技術」を1冊にまとめたのが、
『ディベートの達人が教える説得の技術』です。
読み終えるころには、今までの不完全燃焼感は確実に消化され、「私が話せば、周りは賛成してついてきてくれるはず」
という気持ちに変わるはず!
世の中、いろんな人がいて当たり前。
全員と意見を一致させようとするのではなく、
あなたのすばらしい考えをきちんと伝えることによって、
周りから賛同を得て、賞賛され、評価されるのです!
気持ちのいい議論をした結果、あなたに軍配があがることが
どんなに気持ちのいいことか、ぜひ体験してください。
あらゆる状況で、皆が納得してあなたの意見に賛成してくれる。
それができれば、仕事はずっとスムーズに効率よく結果が出るはず!
このテクニックさえ知ってしまえば、
あなたはもう話し方で損をすることはありません。
■なぜ、主張するほどに人がついてくるのか?
著者の太田龍樹氏は、ディベートの大会5連覇の説得の達人。
なんといっても、その場で勝敗が決まる「対決」をこなしてきた人です。
そして、フジテレビの番組「ディベートファイトクラブ」での闘いっぷりに、中谷彰宏さんがホームページに感動のコメントを残しています。
そんな太田氏が書いたノウハウは、まさに実戦から得たテクニックばかり!
その場で勝負の白黒が出るディベートの試合で、勝ち続けたからこそ伝えられる内容です。
ディベートの試合では、相手を言い負かしても、拍手喝采、感動の嵐となります。
最後には、爽やかな気持ちだけが残り、誰もいやな思いなどしていません。
つまり、誰もが魅力的だと思う話し方さえすれば、勝っても負けても賞賛され、人がついてくるのです。
なぜ、聞いている人が爽やかな気持ちになれるのか?
なぜ、言い負かしても支持されるのか?
相手を言い負かしても支持を得るためには、説得のカラクリがあるのです。
このカラクリさえわかってしまえば、あらゆる状況でもあなたの意見は説得力をもちます。
それこそ、一生使えるあなたの武器となるのです!
■専門分野じゃなくても、圧倒的な説得力!
太田氏は、あらゆるテーマのディベート対決で勝利をおさめてきました。
どんなテーマであっても自信たっぷりに話し、聞いている人の気持ちを揺さぶり感動させ、最後は拍手喝采で締めくくる。
その道の専門家でもないのに!
それどころか、まったく知らなかったことについて議論し、勝利することさえあります。
そんな話術を身につければ、仕事で、プライベートで、あらゆる場面であなたの考えに周りが共感し賛成してくれます。
この本に書いてあるテクニックは、ちょっとしたコツを知るだけで、スグに効果の出るものばかりです。
あらゆる状況で、圧倒的な説得力を持つための「説得の技術」。
ディベートチャンピオンの説得力のノウハウが、ぎっしりつまった1冊です!
- 本の長さ208ページ
- 言語日本語
- 出版社フォレスト出版
- 発売日2006/5/20
- ISBN-104894512254
- ISBN-13978-4894512252
この著者の人気タイトル
商品の説明
出版社からのコメント
心理学者でも弁護士でもありません。
しかし、あらゆるテーマを扱った試合で、勝ち続けてきたのです。
彼こそが、「日常で本当に使える説得術」を知っているのです。
専門家の話は、理屈・理論が中心で、しかも専門的です。
ディベーターでありながら、営業マンとして活躍する著者だからこそ伝えられる、もっとも実践的で現実的な説得の技術!
この本1冊で、今日からあなたは説得の達人です!
抜粋
人の考え方や主張に勝ち負けなどない。
しかし、私は勝敗がその場で決まる「話の勝負」を重ねてきた。
ディベートという「言葉による知的総合格闘技」で、5年連続のチャンピオンを勝ち取ってきた。
議論で勝敗を決めると言っても、ディベートは単なる言葉のゲームではない。
もし、私が相手を空理空論でやりこめるような話し方をしていたら、ディベートでチャンピオンにはなれなかっただろうし、保険営業の仕事でもうまくいくことはなかったであろう。
きっと多くの人から嫌われ、お客様からご契約も頂けず、プライベートでは友達もいない存在となっていたはずである。
ここでお伝えしたいディベートとは、試合のための特別なものではなく、毎日の生活の中でぶつかる困難から、あなたを救うものだ。
ディベート力こそが、あなたの想いをスムーズに言葉にし、周りに伝える大きな手助けとなるだろう。
今となってはディベートキングと呼ばれている私自身が、実はもともと感覚人間だった。
だからこそ、言葉による知的総合格闘技であるディベートで、話し方を磨く必要性を感じていたのだ。
ディベートを知ってからの17年で、私の話し方や説得方法は大きく変わり、あらゆることがスムーズに進むようになった。
今では、これらの経験と知識の中から、営業マンをはじめとして経営者やあらゆる業種のビジネスマン、そして大学生にも教えている。
本書には、実践で勝ち続けたディベート・キングとして、あらゆる必勝テクニックを盛り込んである。
今、PRIDEやK—1のような総合格闘技が注目を集めているように、ディベートこそ、グローバル化が進む世の中で必要とされる話術の知的総合格闘技だ。
つねに勝ちっぷりのよい話し方ができれば、あなたの人生において損をするような話し方はいっさいしないようになる。
それどころか、周りの人々から賞賛を浴び続けることになるのだ。
あなたの主張を伝えて、人々から賞賛される、これほど気持ちのいいことはない。
この最強の話術を身につければ、あなたのすばらしいアイデアや企画を、プレゼンのマズさで残念な結果に終わらせるようなことはなくなる。
ちょっとした話し方のミスや自信のなさで交渉ごとをフイにすることもなくなる。
今日から、あなたの人生は大きく変わるだろう。
毎日が話術のトレーニングの場となる。そして、究極的にはあなたの人間力そのものがつくことを明言しておこう。
毎日人と会い、コミュニケーションする、交渉する、口説く……。その基本となる話し方が大きく変われば、あなたの人生はガラリと変わっていく。
そして、あなたに覚えておいてほしい。「勝つこと=支持を得る」ということを。
だから、私は勝ち続けるほどに支持を得てきたのだ。
本書を読んだ直後から、あなたも自分の主張を通して賞賛される勝ちっぷりのよい話し手になれるだろう。
著者について
桐蔭学園在学中に見た深夜番組をきっかけにディベートに興味を持ち、友人とディベートサークルをつくる。明治大学在学中に、ディベート団体Burning Mindを設立。
現役ディベーターとして勝ち続けながら、企業研修の講師や、日本ベンチャー協議会、専修大学、明治大学でディベートの講師を務める。
ソニー生命保険(株)にてコンサルティング営業に従事。
ディベーターとして大会で5年連続優勝のディベートキング。
主な獲得タイトルは、BMディベートキング(1回防衛)、ミスターBM2002・2003(2年連続)、BMディベートマニア(全国エンターテイメントディベート大会)5連覇、2005「ディベートファイトクラブ」(フジテレビ)に出演し、タレントの伊集院光・なぎら健壱と対戦。
現在、ザ・エンターテイメントディベート Burning Mindの代表を務める。
登録情報
- 出版社 : フォレスト出版 (2006/5/20)
- 発売日 : 2006/5/20
- 言語 : 日本語
- 単行本 : 208ページ
- ISBN-10 : 4894512254
- ISBN-13 : 978-4894512252
- Amazon 売れ筋ランキング: - 1,006,145位本 (本の売れ筋ランキングを見る)
- - 1,012位ビジネス交渉・心理学
- - 1,157位プレゼンテーション
- - 57,967位語学・辞事典・年鑑 (本)
- カスタマーレビュー:
著者について

ザ・エンターテインメント・ディベート BURNING MIND
ファウンダー
ホームページURL: http://burningmind.jp/
高校在学中に観たフジテレビの深夜番組『ザ・ディベート』がきっかけでディベートに興味を持ち、明治大学法学部在学中に、ディベート団体 BURNING MIND(バーニングマインド)を設立。
ディベートを知らない多くの一般の方々にこそ、ディベートの楽しさ・良さをわかってもらうことが大事だと気づき、2001年、この醍醐味・本質を追求するため『ディベートマニア』(社会人ディベーターが「エンターテインメントとしてのディベート」を魅せる大会)を企画。
ディベーターとしては、一部上場企業・有名企業に勤務する数々の猛者・ライバルとガチンコバトルを繰り広げ、『ディベートマニア』6連覇を果たし「ディベートキング」と呼ばれる。2001年からの公式戦戦績は、30戦26勝4敗(テレビマッチを含む)。
7連覇の夢がついえた後、20年以上学んだディベートのさらなる可能性を追求するため、ビジネスでの実戦経験や人間心理を加味した『ネオ・ディベート』(話し方やコミュニケーションにすぐ活かせる新しいディベートの手法)を独自で編み出し、提唱している。
大学・企業・官公庁などで、のべ5000人にのぼる学生やビジネスパーソンにディベートの実用性・面白さを伝えてきた実績を持つ。また、テレビ局の現役アナウンサーにもディベートを教えている。その情熱あふれる講演・セミナーは、毎回「わかりやすい」「やる気が出た」と参加した生徒や受講生の好評を博している。
「日本経済新聞」「週刊ダイヤモンド」「日経ビジネスアソシエ」「日本産業新聞」などメディア掲載多数。過去に、生命保険業界紙である「保険情報」(保険社)にて、「ディベートに学ぶ営業術」を連載。
過去のテレビ番組では、『ディベートファイトクラブ』(フジテレビ)で、タレントの伊集院光・なぎら健壱とガチンコディベート対決。『オビラジR』(TBS)では、オリエンタルラジオの中田敦彦が闘ったディベート(vs品川庄司の品川祐戦、vs千原兄弟の千原ジュニア戦)の実況解説者として出演。『ニッポンの極論』(フジテレビ)では、テリー伊藤や伊集院光らとともに、ジャッジマンとして出演した。
カスタマーレビュー
上位レビュー、対象国: 日本
レビューのフィルタリング中にエラーが発生しました。ページを再読み込みしてください。
- 2006年10月25日に日本でレビュー済みAmazonで購入大人になっていくと相手を説得するしたりコントロールして生活
する事が多くなってくるが、相手から喜ばれたり、尊敬されて、
説得できるならコレに越した事はない!
そんな贅沢な悩みを解決する方法が書かれています。
相手の立場を理解して考えるなど、
相手も行動や仕草などの見方なども詳しく書かれています。
特に本書のミラクルワードは、キターーーーーって感じ!
私も営業の為に人と接する機会が多いですがこの本で新たな
気づきも5つほどありました。明日から即実践できる内容だ
と思いました。
- 2006年8月16日に日本でレビュー済みAmazonで購入私は、帯にも書いてある「主張が通る人はどこが違うのか?」という点について
以下の4つが重要だと考えました。
●筋の通った反論
反論する時は対案を理由と共に提示すること。
→ そして、根拠となる「証拠」を提示し、再度たたみかける。
●仮説を立てて検証
賛成の立場、反対の立場、両方からの問題分析・チェックを行う。
・問題は何か。
・問題点の原因はなにか。
・プランを導入することで、何がどう変わるか。
・問題点を探すこと = 『捨てるための「重要な理由」を探すこと』
●ターゲットの把握
性格や年齢、性別などに合わせた話術を。
●聞き手の気持ちを考える
どんなに話がおもしろくても、座って聞いているだけでは集中力は持続しない。
持ち時間が90分なら、30分1本勝負の3部構成にすべき。
分かっていても、毎回根拠となる証拠を見せるというのは難しいです。
しかし自分の主張を自然に通すには、それぐらいの下準備が必要だということを痛感しました。
- 2010年9月20日に日本でレビュー済みディベートは「言葉による知的総合格闘技」。そう言い切る著者は、こ
の戦いの場で5年連続チャンピオンになったこともあるそうだ。そのチ
ャンピオンにどれだけの価値があるかは不明だが、耳を傾ける言葉は確
かにある。
もっともかっこいい勝ち方とは「51対49で私の勝利になる
ような勝ち方」である。(P19)
相手に反対なら、必ず対案を理由とともに提示する。(P48)
人は希少なものにあこがれる。みんな、ダイヤモンドやら石油
が大好きなのだ。
「今から話すのは、とっておきの話ですからね」
「おそらく、これが聞けるのは日本であなたたちが最初でしょう」
という具合に、希少価値を出して集中してもらうのである。(P84)
戦うということが前面に出過ぎていて、農耕民族である日本人には馴染
みづらいと思う。この本が欧米人の手で書かれていれば、妄信してしま
う人が大量発生してしまうのかもしれないが..
口頭では言い負かされてしまうのかもしれないが、日本語の文章では騙
されないぞ。
- 2008年3月27日に日本でレビュー済みAmazonで購入レビュー数の多さと評価の高さから本書を購入したが、まんまと騙された。
(サ○ラを総動員したのでしょうか)
それはともかく、「なぜか主張が通る人の技術と習慣」というのは何なのか?
本書の主張は全く通りません。というか通す気が少しでもあるのか。
少しだけ例をあげる。
「朝まで生テレビ」を持ち上げているくだりがある。
著者いわく、朝生のパネリストたちは、
(1)きちんとした人であり、
(2)手の置き場所に気を使ってる
とのこと。
どのような点で朝生のディベートが優れているのかまったく説明なし!
さらに朝生の常連の東大教授を絶賛するあたりはひどかった。
話すときの手の動かし方が絶妙だそうな。
そーーーじゃなくて、その教授のディベートのどこが優れているのか書いてくれよ!
巻末に付されている著者のディベートの戦歴(?)はどこで入手できるのだ?
自分で主催した大会に自分で優勝して何が「達人」だ!
ディベートの達人を称するのは本人の勝手だが、
少しくらい「それらしいこと」を書いたらどうだ。
人様に説得の技術を伝授する大先生に、羞恥心という言葉を教えてやりたい。
ほんとはマイナス5点にしたい所だが、残念ながら「星1つ」にせざるを得なかった。
- 2007年11月2日に日本でレビュー済みディベートは、理性の象徴だと思っていた。
人間くさくない、機械的なディベートは嫌だった。
とある時、太田先生の講義を受ける機会があった。
理性とは正反対の感情・情熱の人。
ディベートへの誤解がすんなり解けた。
ディベートを使いこなすためには、まずは感情や情熱が大事なのだと。
そこで、この本を紐解くと、太田先生の処女作ゆえにか、
感情や情熱がほとばしっているのを私は感じてしまいました。
説得とは、説明して納得させることと辞書にはあります。
強引ではない、人を納得するコツがここに書いていることがありました。
それは、人への思いや感情をおもんばかるというコツです。
それら様々なシチュエーションや技をこの本で感じてください。
- 2009年3月25日に日本でレビュー済み本書全体がガツガツし過ぎて、討論のテクニックをレクチャーするというより自己啓発本に近い印象です。期待したテクニックも
・相手の知識に合わせる
・反対するときは対案を出す
・身振り手振りを加える
など、日経なんとかの雑誌に書いてあるようなもの。まぁディベート大会五連覇の達人がお墨付きしてるので信頼性は高い、と言えますが。
総じて赤の他人相手に主張を通すディベート対決という舞台のみ有効なテクニックが多く、一般には使いづらい、というかこの本のテクニックを総動員すると逆にドン引きされるなぁと思いました。飛び込み営業ならともかく、普通にコミュニケーションを取る場面では"共感"を利用する場面が多いので別の本を読んだほうがいいでしょう。
- 2013年8月14日に日本でレビュー済み印象に残っとことは、負けっぷりをよくする必要があるというところです。
負けたとしても、ただ悔しがったり、恥ずかしいと思うだけでは本当に負けたということになってしまう。
しかし、その負けを勝つためのプロセスだと考え、負けた理由を探す事が負けっぷりがいいということだと書いてありました。
私自身、負ける事も楽しみつつ、挑戦していきたいなと思わせて頂きました。
あとは、自分の意見に理由をつける所は出来る方も多いと思うのですが、その根拠となるエビデンスを提示するかしないかが、説得力に大きく影響しているのだと感じました。
内容としては、ディベート関連の本が初めての方には、非常に読みやすい物になっているとおもいます。
ただ、今までにこういった本を多く読まれている方には、少し退屈かもしれません。
そして、この本を読まれるぐらいなら、以前買った本に書いてあった内容を実践する事をおすすめします。
- 2007年11月2日に日本でレビュー済み説得するということは、なにか強引なイメージがあった。
でも、なにか魅惑的な言葉。
それに引きづられてこの本を購入したのだが、
説得をするための、いわば、環境づくりの大事さを教えられた。
目からうろこが落ちた。
言葉だけのやりとりで説得できないということに、
コミュニケーションの難しさもつくづく感じた。
いやはや、コミュニケーションは深いものだ。