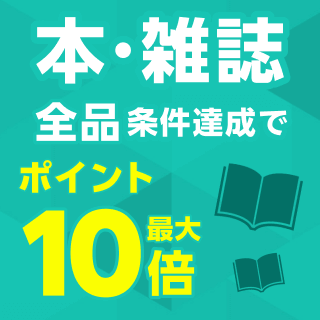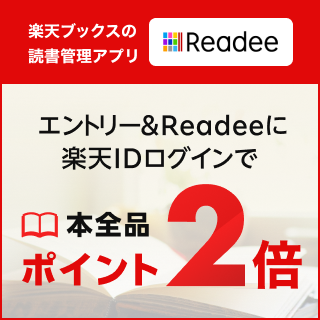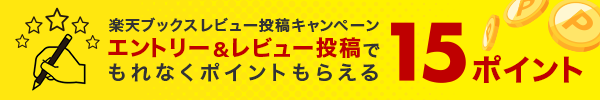羊をめぐる冒険(上) (講談社文庫)
- | レビューを書く
715円(税込)送料無料
- 発行形態:
- 紙書籍 (文庫)
この商品が関連するクーポン・キャンペーンがあります(10件)開催中のキャンペーンをもっと見る
※エントリー必要の有無や実施期間等の各種詳細条件は、必ず各説明頁でご確認ください。
- 【楽天モバイルご契約者様】条件達成で100万ポイント山分け!
- 本・雑誌全品対象!条件達成でポイント最大10倍(2025/4/1-4/30)
- 【ポイント5倍】図書カードNEXT利用でお得に読書を楽しもう♪
- 条件達成で本全品ポイント2倍!楽天ブックスの読書管理アプリを使おう
- 【終了間近!】 条件達成でポイント2倍!楽天モバイルご契約者様はさらに+1倍
- 【楽天Kobo】初めての方!条件達成で楽天ブックス購入分がポイント20倍
- 【楽天全国スーパーx楽天ブックス】最大1000円分クーポンプレゼント!
- エントリー&お気に入り新着通知登録で300円OFFクーポン当たる!
- 楽天モバイル紹介キャンペーンの拡散で300円OFFクーポン進呈
- 【楽天24】日用品の楽天24と楽天ブックス買いまわりでクーポン★
商品情報

商品説明
内容紹介
⇒『羊をめぐる冒険(下)』内容紹介(出版社より)
野間文芸新人賞受賞作
1通の手紙から羊をめぐる冒険が始まった 消印は1978年5月ーー北海道発
あなたのことは今でも好きよ、という言葉を残して妻が出て行った。その後広告コピーの仕事を通して、耳専門のモデルをしている21歳の女性が新しいガール・フレンドとなった。北海道に渡ったらしい<鼠>の手紙から、ある日羊をめぐる冒険行が始まる。新しい文学の扉をひらいた村上春樹の代表作長編。
第一章 1970/11/25
第二章 1978/7月
第三章 1978/9月
第四章 羊をめぐる冒険I
第五章 鼠からの手紙とその後日譚
第六章 羊をめぐる冒険II
内容紹介(「BOOK」データベースより)
あなたのことは今でも好きよ、という言葉を残して妻が出て行った。その後広告コピーの仕事を通して、耳専門のモデルをしている二十一歳の女性が新しいガール・フレンドとなった。北海道に渡ったらしい“鼠”の手紙から、ある日羊をめぐる冒険行が始まる。新しい文学の扉をひらいた村上春樹の代表作長編。
商品レビュー(457件)
- 総合評価
 3.91
3.91
ブックスのレビュー(35件)
-
村上春樹さん 第5弾 羊をめぐる冒険(上)
- かっちゃん Y
- 投稿日:2012年10月25日
●1Q84年や海辺のカフカを読んで、村上春樹さんにはまりました。
●村上春樹さん特集 第5弾 『羊をめぐる冒険(上)』
【内容情報】
あなたのことは今でも好きよ、という言葉を残して妻が出て行った。その後広告コピーの仕事を通して、耳専門のモデルをしている二十一歳の女性が新しいガール・フレンドとなった。
北海道に渡ったらしい“鼠”の手紙から、ある日羊をめぐる冒険行が始まる。
新しい文学の扉をひらいた村上春樹の代表作長編。
●初期の作品です。
●2004年11月15日 発売
●ページ数: 268p
【お勧め度】★★★★★11人が参考になったと回答
-
(無題)
- tyu-tyu-
- 投稿日:2010年12月01日
読み始めは微妙な感じがしましたが、徐々にはまっていきました。
2人が参考になったと回答
-
(無題)
- あひる5413
- 投稿日:2010年08月17日
村上春樹のファンではないので三部作を初めからすべて読んでいるわけではないのですが、これは面白かったです。100%の耳を持つ女の子、日本にいないはずのひつじ、それを探す政界大物の秘書など多様な人物が入り乱れる上巻。一気に読んでしまいました。
2人が参考になったと回答
ブクログのレビュー(422件)
- 投稿日:2025年03月17日
前作のピンボールよりも物語性が強くなって読みやすいと感じた。
キャラクターの会話劇が独特な言い回しでラノベだけれど西尾維新的な(?)ひねくれさが妙にツボ。
主人公の僕が自分の子供を持つことに対する価値観が自分と重なってめっちゃ共感した。 - 投稿日:2025年03月09日
「風の歌を聴け」「1973年のピンボール」ときて、「羊をめぐる冒険」について集大成感があったかと言えばあまりそんなことは感じられなかった。ただ、相変わらず前作と共通した要素はあって、「適度な運動」「SEX」「闇」はこれまでも、そしてこれから(海辺のカフカ)も村上春樹の要素としてあり続けている。
集大成感もないし、全体として綺麗に何かを言うこともできない。一言でいえば、これまでやこれからの作品と比べて好きではない、だが、もしかするとここでそのように断言するのは時期尚早かもしれない。というのは、「まだ私が何かを感受するには未熟過ぎるのかもしれない」などという最高に抽象的な言い訳という類のものではなく、読む側の「精神状態」に関することである。というのも、これまで私が村上春樹作品に触れていた時期は「笑気麻酔」やら何やかんやら、一言で言えばメンタルがやられていた時期と重なる。実際、「1973年のピンボール(僕に惹かれて)」では「彼らが孤独を感じ、未来を憂いているということが、尚のこと私を安心させ、この世界に深く共感するのである。」というようなことを述べている。そして、今それらを客観視できていることが何よりの証明となるが、その頃と比較した私のメンタルは現状安定していると言える。つまり、危機は去った。だから、私はそれまでと比較して村上春樹の陰鬱な世界にそれほど共感或いは必要性を感じないのかもしれない。だがまあ、そうは言っても結局本作は私にとりまあまあなのだろう。
しかし、だからと言ってスッパリと話を終えようなどという気はない。良い読書というものは我々の思考を刺激するから良いので、如何に「羊をめぐる冒険」がまあまあな作品だとは言っても、それは何らの刺激性もないというレベルからは程遠いのである。
「ちょうどある種の人々がカレンダーの数字をひとつずつ黒く塗りつぶしていくよう」(1)な、「僕」特有の不幸な時間感覚で営まれる生活のルーティンに「読書」が含まれるということについて思うところがある。「それから三日が無為のうちに過ぎた。何ひとつ起こらなかった。」(2)この昭和の読書家青年にとり、読書は無為の要素の一つでしかなかったようだが、私にとってはそうではない。その理由の一つは個人的で、もう一つは一般的である。個人的な方から言うと、私はかつて小学生時代まで無類の読書家だった。その頃私は休み時間に足繁く図書室に通い、誕生日プレゼントに小説を買ってもらっていたりした。だが、中学に入る時分、親がついにデビューした「スマホ」がそういう良識な文化的体験を根こそぎ刈り取ってしまい、私の日常から読者は消え失せ、次に再開する大学2年までのおよそ7年間の空白が生まれたのである。現在の私の読書への執着ぶりは十中八九空白期間の反動であろうが、とにかく今や私にとって人生の目的、相棒と言って差し支えのない「読書」は当然のことながら、無為とは程遠いのである。長くなったが、これが個人的な理由である。一方で一般的な理由は、スマホの登場によって読者の価値が一般的に高尚になったことである。それの是非は置いといて、多くの(人間の割合的には少ない)読書家は今や堂々と、特別的な気持ちで読者に励んでいるのではなかろうか。先に引用した箇所からは、そうなる前の読書(今で言えばYouTubeのショート動画を眺める事などに置き換えられるのだろうか)の価値の片鱗を見て取ることができる。 - 投稿日:2025年02月26日
風の歌を聞け、1973年のピンボールは結構好きだったので続編に期待して読んだ。中盤結構きつかったが、下巻に期待。
お気に入り新着通知
- 未追加:
- 2件
ランキング:文庫
※1時間ごとに更新
-
1

-
【入荷予約】火喰鳥を、喰う
原 浩
792円(税込)
-
2

-
マスカレード・ゲーム
東野 圭吾
990円(税込)
-
3

-
ファラオの密室
白川 尚史
840円(税込)
-
4

-
青い壷 新装版
有吉 佐和子
847円(税込)
-
5

-
おやごころ
畠中 恵
836円(税込)
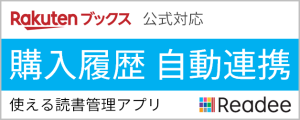


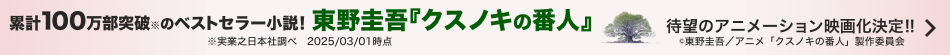
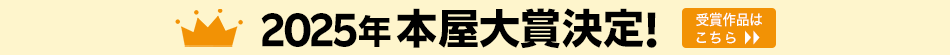
![羊をめぐる冒険(上)(講談社文庫)[村上春樹]](http://shop.r10s.jp/book/cabinet/9121/9784062749121_1_13.jpg?fitin=560:400&composite-to=*,*|560:400)
![羊をめぐる冒険(上)(講談社文庫)[村上春樹]](https://tshop.r10s.jp/book/cabinet/9121/9784062749121_1_13.jpg)