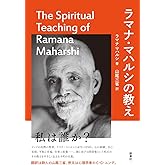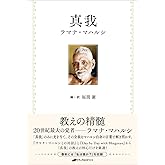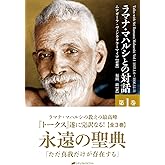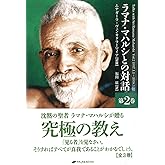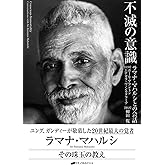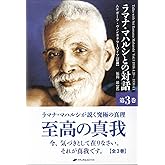「自己」( “真我・実在・それ” を、本書では主に “自己” と表記しています) について
様々な角度から 多様な言葉の表現で、
しかも あくまでシンプルに尽きる答えが、繰り返されています。
求めている「自己」は、いつか到達するものではなく すべての思考が止んだ、そのまま・ありのままの 自然な静寂であり、
その永遠の静寂が 文字どおり、 自他なくすべてを包含する 「すべて」、私たちはすでに「それ」である……
ということが、何度も 根気強く 質問者に対して語られています。
本書の中では『マハルシの福音』が個人的には初見だったので、新鮮でした。
どの書籍でも マハルシの教えは常に一貫していますが、ストレートに 「それ・意識」を表している言葉は、何度味わっても 内に喜びを感じます。
あと、本書に関しては絶版ということもあり、結構な高額になっている時期も多いようです。タイミング、重要ですね。

無料のKindleアプリをダウンロードして、スマートフォン、タブレット、またはコンピューターで今すぐKindle本を読むことができます。Kindleデバイスは必要ありません。
ウェブ版Kindleなら、お使いのブラウザですぐにお読みいただけます。
携帯電話のカメラを使用する - 以下のコードをスキャンし、Kindleアプリをダウンロードしてください。

ラマナ・マハリシの教え ペーパーバック – 1993/6/1
このページの読み込み中に問題が発生しました。もう一度試してください。
- 本の長さ212ページ
- 言語日本語
- 出版社めるくまーる
- 発売日1993/6/1
- ISBN-104839700168
- ISBN-13978-4839700164
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
ページ: 1 / 1 最初に戻るページ: 1 / 1
登録情報
- 出版社 : めるくまーる (1993/6/1)
- 発売日 : 1993/6/1
- 言語 : 日本語
- ペーパーバック : 212ページ
- ISBN-10 : 4839700168
- ISBN-13 : 978-4839700164
- Amazon 売れ筋ランキング: - 503,270位本 (本の売れ筋ランキングを見る)
- - 17,319位哲学・思想 (本)
- カスタマーレビュー:
著者について
著者をフォローして、新作のアップデートや改善されたおすすめを入手してください。

著者の本をもっと見つけたり、似たような著者を調べたり、おすすめの本を読んだりできます。
カスタマーレビュー
星5つ中4.4つ
5つのうち4.4つ
14グローバルレーティング
- 星5つ星4つ星3つ星2つ星1つ星5つ75%7%0%18%0%75%
- 星5つ星4つ星3つ星2つ星1つ星4つ75%7%0%18%0%7%
- 星5つ星4つ星3つ星2つ星1つ星3つ75%7%0%18%0%0%
- 星5つ星4つ星3つ星2つ星1つ星2つ75%7%0%18%0%18%
- 星5つ星4つ星3つ星2つ星1つ星1つ75%7%0%18%0%0%
評価はどのように計算されますか?
全体的な星の評価と星ごとの割合の内訳を計算するために、単純な平均は使用されません。その代わり、レビューの日時がどれだけ新しいかや、レビューアーがAmazonで商品を購入したかどうかなどが考慮されます。また、レビューを分析して信頼性が検証されます。
上位レビュー、対象国: 日本
レビューのフィルタリング中にエラーが発生しました。ページを再読み込みしてください。
- 2015年3月23日に日本でレビュー済みAmazonで購入
- 2012年9月24日に日本でレビュー済み何冊も持っていて、10数年読み続けた本ですが、すべて人に上げてしまいました。
英語の原書ももっていましたが、見当たりません。
日本語の古書を買おうとしましたが、7000円! マハリシも驚く値段ですね。
日本がいま、いかに物質的になったかという証左でしょう。
有史以来、たくさんの人が、最高の境地に至りましたが、それは一瞬であったり、後に何度か訪れるまれな体験でした。
マハリシはその体験が一生続きました。
教えはシンプルですから、英語もシンプル、翻訳された日本語もシンプルでした。
しかし、シンプルな言葉は本当にシンプルでしょうか?
色盲の人に聞けば、色のない世界ではない、黒と白の間に数百万の階調がありそのひとつひとつが印象的だと言うでしょうね。
ヘレン・ケラーは、目が見えず、耳も聴こえない人でしたが、部屋に友人たちがいると、誰が誰だかわかりました。
目や耳が邪魔をしているのです。
五官が邪魔をしています。
その五官を曇らせて、五官の本来の仕事である真実を求める機能を損なうのが、欲望です。
「わたしが」と言うとき、わたし+が=我、ですから、すでに我=エゴ=欲望が出ています。
「あなたが」と言うとき、あなた+が=我、ですから、相手をエゴの目で見ています。
美食欲、物欲、色欲、権力欲、その他もろもろの欲(我から派生するもの)を捨ててシンプルになれば、真我が輝き出します。
むしろ、辞書を引きながら、シンプルな英語で、マハリシ(マハ=偉大な、リシ=賢者)に想いを馳せましょう。
マハリシは私、そしてあなたのそばに、昔から、いま、そして未来も、いつも存在しています。
英語版はアマゾンUSで購入できます。
The Spiritual Teaching of Ramana Maharshi [Paperback]
Ramana Maharshi (Author)
Price: $10.10
お値段は800円。送料込みで23ドルの1800円ほどでした。
- 2022年11月18日に日本でレビュー済みAmazonで購入難しくて、私には難しいです。途中から読む気になれず断念しています。
- 2018年12月22日に日本でレビュー済みいつもここに戻って来ます、the Self に。今は亡き山尾三省氏の訳。座右の書。あなたも是非お手元に。
原書もあればベスト!
「幸福とは何でしょうか?」
「幸福は、自己(真我)の本性そのものである。幸福と自己は別のものではない。世界のいかなる対象物の中にも幸福はない。」.(p.33)
- 2018年1月4日に日本でレビュー済み初めてこの本を読んだとき、私は自分の心が電気と言うか稲妻にでも打たれたような感覚になりました。
過去、誰でも一度は本当の自分を知りたい、自分探しをしたいと思ったことがあるのではないでしょうか。
この本は明らかにその答えを私たちに伝えていると私は思います…思いますが、だがしかしです…読めば一瞬のその言葉、この「ラマナ・マハリシの教え」を心の底から納得出来るていると自分に嘘をつけずに言えるかどうか?頭で、真我の探求において「私は誰か」と言う思索と瞑想の実践が最重要と分かっていても、どれほどそのことが自分の支えになっているのか?もっと言うと、道元禅師も仰る「生死一大事」の特に「死」に際してもなおそれは自分に有効なのか?…実際は、この部分は生涯かけて取り組むに余りある課題です。きっと、自己のうちに総てがあると揺ぎ無く自認できるまでそれは続くのでしょうけど…
この本は悩み多きこの時代にこそ必要なのではないかと思えてきます。もし、多くの人がこの理解を持つことができたなら、この世の争いは金輪際(←死語かな)無くなるかも知れません。それほどのインパクトのある本だと私は思います。特に瞑想を行う人であれば必携な本です。
- 2015年6月5日に日本でレビュー済み一般に流布している瞑想は、ウパニシャッド由来である。
B.C.8世紀のウッダーラカ・アールニが確立した「有」の哲学と、自己(アートマン)の能力を全能の神(ブラフマン≡真実語≡真言)と神秘的同値させる「ウパース(念想)」が結びついて誕生した瞑想が、「観(ヴィパッサナー)」の瞑想の始まりである。「有」の瞑想とも呼ぶ。
主体の自己Aと客体の他者Bとを同値させるので、A is B である。
客体Bを「空」(無所)としたのが、B.C.5~6世紀の釈尊がアーラーラ・カーラーマ仙人から学んだ「無所有処定」(四無色定の第三番目)である。これは客体Bの「空」を主体Aが「有」であると同値させる「観」の瞑想である。
一方、B.C.7世紀のヤージュニャヴァルキヤは、『自己(アートマン)は純粋な意味で認識の主体に他ならないのであるから、決して対象にはなりえない。自己(アートマン)は把握することも表現することも究極的には不可能である。従って、自己(アートマン)は「~ではない、~ではない」(ネーティ、ネーティ)としか言いようがない』という「五蘊非我」の哲学を確立する。これが「止(サマタ)」の瞑想の始まりであり、「無」の瞑想とも呼ぶ。
主体の自己Aと客体の他者Bとは同値させられないので、A is not B である。
このAもBも「空」としたのが、B.C.5~6世紀の釈尊がウッダカ・ラーマプッタ仙人から学んだ「非想非非想処定」(四無色定の第四番目)である。客体Bを「空」としたのが「非想」であり、主体Aを「空」としたのは客体Bの「空」とは異なるので「非非想」となる。これが主体も客体も「空」であるとする「止」の瞑想である。
マハルシ師も釈尊もこうした瞑想を勧めない。なぜか?
それは主体(私)と客体(私のもの)という二元性を前提にしているからである。
釈尊は、主体と客体の前提を「身見」という煩悩と名づけ、欲界(人間界)の無知の最大原因だと指摘する。
***
『私は誰か』の第2頌は、『今述べたことのすべてを「これではない」、「これではない」と否定し去った後に、ただ一つ残る自覚、それが私である。』と述べる。
この意味は、「止」の瞑想の後、「ただ一つ残る自覚」である真我(アートマン)に気づく、という訳である。唯識仏教の「阿頼耶識」も、本当は「真我」を指していたのである。
釈尊は「アートマン」を否定したと言われているが、それは間違いである。客体Bを「アートマン」とする「観」の瞑想を否定したのである。なぜなら、マハルシ師が非二元性の「真我」として説明する内容は、釈尊が説く非二元性の「涅槃」と同一だからである。
- 2007年1月19日に日本でレビュー済みまず、装丁がとても良い。
ラマナ・マハリシの他の本も同様だが、インドの聖者の本といえば、表示に大きく写真をプリントしたものが多い。別に悪くはないのだが、それは、これら聖者の教えにちょっと触れてみようという読者を逃している可能性は多いと思う。
それらに比べ、本書は、落ち着いた色の表紙に描かれたマハリシのシンプルなイラストが良い雰囲気である。また、紙質は真っ白ではなく、ややザラザラして変色もしやすいかもしれないが、質素な感じが、マハリシの偉大だが素朴な教えと良く合っている。
実際には、ほとんど会話をしないと言われる沈黙の聖者の貴重な言葉を、さらに厳選して簡素に表現したようで、どこから読んでも良いが、2、3行読んだらその内容について黙想したくなるような霊的な教えに満ちている。マハリシは半世紀も昔に亡くなったが、その師を現前に感じるような書である。
- 2008年4月21日に日本でレビュー済み初期のラマナの邦訳として、南インドの瞑想もありますが、当時こちらを良く読みました。
ラマナの教えが簡潔に書かれているものですが、当時はとても共感し、自己探求にひたむきになれた欠かせない本でした。
今は絶版のようですが、その後たくさんの邦訳が出版されましたので、そちらをご一読ください。